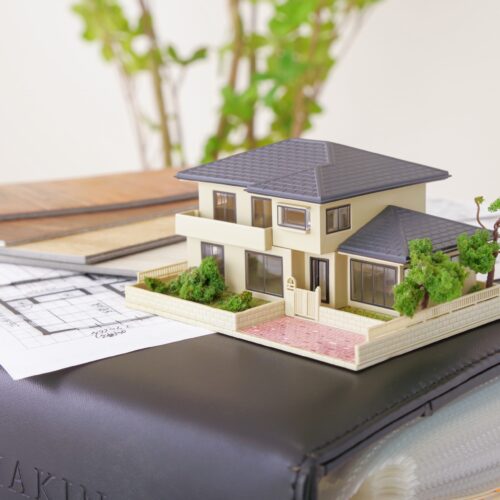防音の部屋を作るにはー家と楽器と近隣のために検討する6点

注文住宅情報コラム
COLUMN
【営業】 阿部 栄樹

今お住まいの家で「楽器の練習をしたい」「オーディオルームを作りたい」などのご希望はありませんか?
そのような場合は、今ある部屋を利用し、防音工事(防音リフォーム)を実行しなければなりませんね。
もしくはこれから家を考えるというご家庭であれば、最初から防音の手当てをした部屋を一室作っておきたいものです。
近隣住民間でのトラブルの多くは、騒音によるものです。 この不要なトラブルを防ぐためにも、家で音を楽しむためにはそれなりの手当てが必要です。
まずは、音がご近所へ伝わる仕組みを理解し、それらに対応するためのケアやコストについて考えてみましょう。
1.音は、「空気」「建物」それぞれの振動で外部へ漏れる
既にご存知の通り、音は、空気を揺らすことで「音」として認識されます。
また、楽器やスピーカーなどが触れる床や壁が揺れることでも「音」として認識されることがあります。 このため、防音でとても大事なのは「部屋と外部との遮断」なのです。 基本中の基本ですから、「何をいまさら」とおっしゃるかもしれません。
ですが、外部と完全に遮断してしまうことは、一般住宅ではとても難しい事です。 木造住宅であれば、外壁と内壁の間には通常、空気を含んだ空間があります。 細かな話をすれば、配管も外部とのつながりの一部です。
このようなことから、家における防音は、細心の注意と知識・経験の必要な工事であることを理解してください。
2.防音にはレベルがある?
楽器演奏のための防音工事をお考えの場合、その楽器に適した防音のレベルがあることを知っておきましょう。
ご存知の通り、音の大きさを表現する場合「デシベル(dB)」で表します。
- 木の葉がすれ合うカサカサとした音=20デシベル
- 会話=60デシベル
- 地下鉄の駅に電車が近づいてきたときの音=100デシベル
- 飛行機が飛んでゆくとき空港(機外)で耳にする音=120デシベル
日常生活で私たちが触れる音は、粗方こういった数値となっています。
これを楽器に置き換えた時、
- ギターの音=80デシベル
- ピアノの音=100デシベル
- ドラムの音=120デシベル
と言われます。
どうでしょうか。 楽器の音が100デシベル近辺であるとしたなら、先に挙げた地下鉄の音とほぼ同等の音を出していることになるのです。 防音はとても大切な事であることをご理解いただけたのではないでしょうか。
これら楽器の音を近隣の迷惑にならないよう防音対策を施す際に検討されるのが、「遮音等級(Dr等級)」といい、JIS規格で定められている基準です。
ドラムをご近所迷惑にならないようにしたい場合は、「D-65」~「D-75」程度の遮音等級が必要です。
3.防音したい部屋の用途や使用する機器(楽器)により防音工事はさまざま
先にも挙げた通り、楽器により数値がかなり変化します。
また、楽器を演奏する時間帯によってもどこまでの防音が求められるのかも重要な検討事項でしょう。 更に、家の構造(木造か、コンクリート系なのか)で施工方法も大きく変わります。
このため、ごく一般的な木造住宅で楽器のための部屋を設けたい(リフォームしたい)ケースを考えてみたいと思います。
「グランドピアノを昼夜関係なく弾きたい」
このような場合は、最低でも「Dr‐50」以上は欲しいところです。
壁・床・天井にはグラスウールや防音パネルといったものを導入し、楽器が床に触れる部分の振動を抑えるためにゴムパッドを敷き込むなどが最低限の施工でしょう。 楽器室の内壁を完全に取り換えるケースもあります。 外部との接点である窓を極限まで小さくし、防音サッシを入れなくてはならないこともあります。
おおよその目安は、6畳で300万円~。
ご近所の建物との位置関係により配慮する点も増える可能性があること、築年数によっては内壁を取り除いた段階で柱の傷みが発見されることもあり得ますから、予算には余裕を持って考えておきましょう。
4.意外に重要なのは、「空調」
楽器を設置するにしても、オーディオ機器を設置するにしても、空調はとても大切な側面です。
高温や多湿が楽器を傷めることは良く知られていることです。 そのため、新たにエアコンを入れることも必要となるでしょう。
このエアコン導入ができるかどうかも、希望の部屋に防音対策を施す価値があるかどうかの見極めポイントとなります。
このエアコンの配管部分も、外部との接点となります。 このような細かな点にまで配慮できる建築家やリフォーム業者を選ばなければ、後々の後悔につながってしまいます。
5.音には音のスペシャリストがいる
楽器演奏のための部屋やオーディオルームは、一般の部屋とは異なる配慮が必要であることはご理解頂けたと思います。
防音工事と一言で言っても、先に挙げた通り、楽器の種類や演奏する時間帯、近隣との関係など、トータルでの配慮が必要ないわば「専門職」。 通常の戸建て住宅でも、「子供の声がうるさい」などの苦情が発生していることを考えると、更に経験と知識が必要なのです。
ドラムなど、単に音だけでなく振動も気になる楽器でしたら、部屋の中にもう一つ部屋を設ける(内壁を更に設けて通常の壁とは極力接点を持たせないような内側の囲い)施工も必要なケースすらあるのです。
こうなると、住宅建築+音響への造詣が深い建築家やリフォーム業者の力が必要です。 「楽器 防音」などのキーワードで検索すると、その防音室の構造についての解説が出てきますので参考にしてください。
6.予算がないけれども、楽器室が欲しい場合は
これから新たに家を建てる場合は、音に対して知識を持つ建築家の知恵を借りることもできるでしょう。
ですが、既に存在する家の一室を楽器室にしたい場合、手っ取り早い方法が一つだけあります。 「防音ブース(組み立て式防音室)」を購入することです。
YAMAHAやカワイなど楽器メーカーなどから発売されていますから、まずはサイトを覗いてみてください。 50万円程度からあり、遮音等級も各種あります。 演奏したい楽器や、必要なスペースに合わせてチョイスできるのが、気軽でよいと思われるかもしれません。 楽器を取り扱うお店で、中古の防音ブースが販売されていることもあります。
ですが、どうしても部屋の一部がデッドスペースになってしまうことや、空調の取り付けが難しいことがデメリットとして挙げられます。
そのため、
- 予算が限られている
- 賃貸マンションでの楽器室を考えたい
- 家の建て替えまでのつなぎ
などのようなケースで使われることが多いようです。
ケースバイケースで予算・手法も様々
一言で「防音」と言っても、楽器や求められる遮音等級、家の建て方や状態により手当は様々であることが理解できました。
そのため、予算も一概にはくくれないこともご理解頂けたのではないでしょうか。 ですが、本格的に防音の部屋をひとつ作ろうとすると、最低でも300万円は覚悟しなければなりません。
音響には音響のプロがいるように、家の一部屋を防音するにも知識と経験がモノを言います。 音響に詳しい建築家か、楽器室を専門に施工している「防音業者」に依頼するのが正しい方法と言えます。 数百万円の単位のお金ですから、「さほど効果がなかった」という後悔は絶対に避けなければなりません。
また、一方では、楽器メーカーが販売する「組み立て式防音防音ブース」という選択肢もありました。 若干の不便はあるものの、設置がラク、費用面でも気軽でよいという商品でした。
近隣トラブルにもつながりかねない音の問題であるだけに、可能な限り手を尽くすに越したことはありません。 生活を豊かにする趣味ですから、誰にも邪魔されたくないですし、ご近所の迷惑になるようなことは避けなくてはなりません。
納得のゆくまで相談し、アフターサービスについてもきちんと確認しておく必要があるでしょう。